府中町の特別支援教育の現状と課題について 2020年12月議会 一般質問
もくじ

●はじめに
障害による学習上や生活上の困難をかかえている児童生徒は、2018(平成30)年現在、全国で約45万2千人おり、全児童生徒数の4、6%です。2008(平成20)年度との比較ですが、特別支援学校1.2倍(約7万3千人)、特別支援学級2.1倍(約25万7千人)、通級による指導を受けている小中学生が2.5倍(約12万3千人)となっています。
学習上や生活上の困難をかかえている子どもに対して、その可能性を最大限に伸ばすために、障害の状態に応じて一人ひとりにあった適切な指導と支援が必要であり、特別支援教育の充実が求められています。
1.特別支援教育とは
文科省の定義によりますと「特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う」とされています。
そのために、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導という3つの学びの場が用意されています。
特別支援学校は、障害の程度が比較的重い子供を対象として教育を行う学校で、1学級の標準は6人(重複障害の場合3人)。対象とする障害は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱(身体虚弱を含む)です。
特別支援学級は、小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級で1学級の標準は8人。知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害といった障害の種別ごとの学級が編成されます。
通級による指導は、障害のある子どもが小・中学校の通常の学級に在籍し、ほとんどの授業(主として各教科などの指導)を通常の学級で行いながら、週に1単位時間~8単位時間(LD、ADHDは月1単位時間から週8単位時間)程度、障害に基づくさまざまな困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態です。対象とする障害は言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由及び病弱・身体虚弱です。
町内には特別支援学校はありませんので、特別支援学級と通級指導について伺います。
①町内で、特別支援学級に通う児童生徒数および「通級による指導」を受けている児童生徒数の推移はどうなっているでしょうか。
◆教育部長 提出資料にも示しているとおり、過去5年間の児童生徒の推移をみてみますと、特別支援学級在籍の児童生徒の数は平成28(2016)年度には小中全体で62人でしたが令和2(2020)年度では90人と5年間で約1.5倍、また、通級指導教室では、平成28年度18人が、令和2年度50人と約2.8倍になっております。このように特別支援教育についての理解が年々高まり、指導を受ける児童生徒の数が増えている状況にあります。
2.特別支援学級の特徴
二見議員 つぎに特別支援学級について伺います。
特別支援学級に通っている児童生徒のうち、知的障害のお子さんが約47%(12万1千人)、自閉症ならびに情緒障害のお子さんがやはり約47%(12万3千人)で、知的障害、自閉症、情緒障害をもつお子さんが多い。その他は約5%です〔2018(平成30)年度〕。
(1)まず、知的障害ですが、知的障害のあるお子さんで特別支援学級の対象となるのは、「その年齢段階に標準的に要求される機能に比較して、他人との日常生活に使われる言葉を活用しての会話はほぼ可能であるが、抽象的な概念を使った会話などになると、その理解が困難な程度のもの」とされています。
文科省の「教育支援資料」*1はさらに次のように説明しています。
例えば、日常会話の中で、晴れや雨などの天気の状態について分かるようになっても、「明日の天気」などのように時間の概念が入ると理解できなかったりすることや、比較的短い文章であっても、全体的な内容を理解し短くまとめて話すことなどが困難であったりすることである。
*1)文科省初等中等教育局特別支援教育課『教育支援資料 ~障害のある子供の就学手続きと早期からの一貫した支援の充実』(平成25年10月)
(2)つぎに自閉症ですが、「自閉症とは、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする発達の障害」です。
(3)第三に情緒障害ですが、情緒障害とは、状況に合わない感情・気分が持続し、不適切な行動が引き起こされ、それらを自分の意思ではコントロールできないことが持続し、学校生活や社会生活に適応できなくなる状態を言います。
自閉症・情緒障害をもつお子さんは、①他人とかかわって遊ぶ、自分から他人に働きかける、集団に適応して活動する、友達関係をつくり協力して活動する、決まりを守って行動する、他人とかかわりながら生活を送ることなどが難しい。②言語が全くなかったり、言葉の発達の遅れや特異な使用が見られたりする、などの特徴があります。
そこで質問です。
②当町において特別支援学級はどのようになっているでしょうか。
◆教育部長 特別支援学級は、障害種別ごとに学級を設置しており、児童生徒の障害の状態等に応じて、個々に具体的な目標と内容を設定し、授業を実施しております。
例えば、知的障害の特別支援学級においては、教科の学習で日常生活と関連付け、学習と体験を関連付けた指導を取り入れております。
具体的には、野菜を育て、収穫した作物を使って調理を行う際に、材料の分量を計算したり、栄養教諭に調理の方法でわからないことを質問したりする学習の中に、伝えやすく話をするための文章を考え、伝える学習を仕組んだり、計算や語彙の力を高めたりするなどの学習を体験的な活動の中に積極的に取り入れております。
特別支援学級は児童生徒数1学級あたり上限8名となっており、障害種別ごとに8名を超えると学級数が増えます。
令和2(2020)年度は、知的障害、自閉症情緒障害、肢体不自由、病弱などの特別支援学級を町内小中学校全体で21設置しております。
また、特別支援学級には、教員以外に町単独費で教育支援員を配置し、障害の状態に応じた丁寧な指導ができるよう、町として取り組みを進めております。

3.通級による指導の特徴
二見議員 第3に「通級による指導」について伺います。発達障害などで通級指導を受けている児童生徒が昨年(2019年)5月1日時点で13万4千人に上り、過去最高になったと文科省が公表しました。内訳は小学校11万7千人、中学校1万7千人、高校8百人です。
障害種別でみますと▽言語障害4万人▽自閉症2万6千人▽注意欠陥多動性障害(ADHD)2万5千人▽学習障害2万2千人です。
注意欠陥多動性障害(ADHD)とは、「身の回りの特定のものに意識を集中させる脳の働きである注意力に様々な問題があり、又は、衝動的で落ち着きのない行動により、生活上、様々な困難に直面している状態を言います。
これまであまり知られてこなかった障害の一つで、「注意欠陥多動性障害」という診断名は、1994年からだそうです。
活動に集中できない、気が散りやすい、物をなくしやすい、順序だてて活動に取り組めないといった「不注意」と、じっとしていられない、静かに遊べない、待つことが苦手で、他人の邪魔をしてしまうといった多動衝動性が、同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に、強く認められます。
「故意に活動や課題に取り組むことを怠けている」「自分勝手な行動をしている」などとみなされてしまい、これまで障害によるものだと理解されてきませんでした。そのため、まわりの大人から行動を強く規制されたり、叱られることも多く、そこから「自分はどうせ、何をやっても叱られる」といった無力感に陥ってしまうこともあります。
学習障害も知られるようになったのは比較的最近です。
学習障害とは、学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態を言います。
全般的な知的発達に遅れはないのですが、聞く、話す、読む、書く、計算すること、推論する能力のうち特定のものが苦手です。
学習障害は、まだ十分に知られていないうえに、一部の能力を習得することと使うことだけが難しいので、「単に学習が遅れている」「本人の努力不足」とみなされてしまい、障害だとは思われていない。
柳家花緑さんという落語家がいますが、識字障害(ディスクレシア)という学習障害があることを公表しています。書かれた文字を見て脳が認識して理解するのに時間がかかる障害です。書くことも難しい*1。
*1)落語を聞きにきたお客さんにサインするとき演目の「芝浜」と書いて欲しいといわれて「浜松やりました」と書いてしまった。古典落語中の名作であり、「芝浜」という字は何千回、何万回と見てきたのに字が出てこない。(柳家花緑『僕が手に入れた発達障害という止まり木』幻冬舎)

花緑さんは「字が読めないために勉強全般に興味がなくなった」と言います。「教科書が読めないし、黒板に書かれたことをノートに書き写すこともできないので、クラスメイトが先に進むのに、おいていかれてどんどん差が広がっていく。字を読むのが苦手だから宿題もできない。その積み重ねで、勉強からますます遠ざかっていく」。小学校5年生のときの通知表に担任の先生は「気が散って学習に身が入りません」「根気よく復習しましょう」「勉強以外のことなら一生懸命やるのですが…」と書いていますが、40年ほど前ですから、担任の先生も障害だとはもちろん知らない。
花緑さんの本名は小林九というそうですが、「小林君は勉強しない子」という評価となり「もっと努力しなさい」というふうになるわけです。そして同級生は「バカな小林くん」と呼ぶ。落語のおかげで花緑さんは酷いいじめにはあわなかったようですが、発達障害のあるお子さんは学校でいじめられることが多く、いじめから不登校になる場合も少なくありません*2。
*2)島崎由貴らが関東(1都6県)の公立中学校の養護教諭を対象に行ったアンケート(回答266人)によると「発達障害のある生徒が背景に抱えている問題」の1位が「友人関係上のトラブル・いじめがあった」であった。「中学校における不登校・発達障害の生徒の傾向と支援の現状についての調査研究」(『東京学芸大学教育実践研究センター紀要』第5集、2009年)
文科省によりますと注意欠陥多動性障害や学習障害など発達障害の可能性がある児童生徒は全体の6.5%程度だと言われています*3。
*3)文科省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」
そういうなかで、通常の学級に在籍しながら週に1単位時間から8単位時間程度、障害に基づくさまざまな困難の改善・克服に必要な特別な指導を特別の場で行う「通級による指導」が1993(平成5)年より全国で制度化されました。2006(平成18)年からは学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症が対象に含まれるようになっています。
そこで質問です。
③「通級」の指導の特徴、指導の実際はどのようなものでしょうか。
◆教育部長 府中町では、通級指導教室を平成26(2014)年度に府中南小学校に設置し、指導をスタートしております。
この通級における指導は、小中学校に在籍する児童生徒のうち、障害による学習上または生活上の困難の改善・克服をすることを目的とし、週1時間から週2時間程度、障害に応じた特別の指導を実施しております。
現在、府中町では、小学校2校、中学校2校に通級指導教室を設置し、教員を配置しており、教員が配置されていない学校で、通級の対象となる児童生徒が在籍している場合には、教員が巡回し、指導に当たっております。
例えば、自閉症の場合は、他者と社会的な関係を形成することに困難を伴い、コミュニケーションの困難さや情報をとらえることが困難であるなど、通常の学級の一斉指導のみでは十分な成果が上げられない場合があります。そのような場合に、円滑なコミュニケーションのための知識や技能を身につけるための指導を個の実態に応じて指導し、その上で、絵や写真などの視覚的な手掛かりを活用しながら相手の話を聞くことやメモ帳を用いて自分の話したいことを相手に伝えるなど、実際に学んだ知識・技能を生活の中で実際に活用できるよう学びの場面の設定を行っております。
また、注意欠陥多動性障害の場合は、どの場面で困難さが生じているのか状況の要因を明らかにし、例えば、衝動性・多動性が強い場合は、ロールプレイを取り入れ相手の気持ちを考えたり、ビデオや絵で視覚的に示したりすることで、自分や周りの状況を振り返るなどの指導を行っております。
学習障害で、書くことが困難で、適切な文字をなかなか思い出すことができない場合は、パソコンで文章を書いたり、ノートをパソコンで取ったりすることにより授業内容を書くことができるようにしております。
通級による指導を受ける児童生徒に係る週あたりの授業時数については、当該児童生徒の心身の障害の状態を十分考慮し、保護者と連携を図り、時間設定を行い指導しています。
4.教育支援委員会
二見議員 第4に教育支援委員会について質問します。文科省の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」は、教育支援委員会について次のように述べています。
「現在、多くの市町村教育委員会に設置されている『就学指導委員会』については、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、『教育支援委員会』(仮称)といった名称とすることが適当である。『教育支援委員会』(仮称)については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待される」。
④文科省は「教育支援委員会」に以上のような位置づけを与えていますが、当町において教育支援委員会はどのような役割を果たしていますでしょうか。
◆教育部長 教育支援員会は、障害により教育上特別な配慮を要する児童生徒に対し、その就学について適格に判断を行うために設置しており、11月に本委員会を実施している他、必要に応じて持ち回りによる会議を実施しております。
委員は府中町立学校教職員(各校の校長と特別支援教育コーディネーター)と関係行政職員(福祉課、子育て支援課の職員)から構成しています。
また、専門的な立場からの助言をいただくために顧問(療育関係者、病院の院長、特別支援教育アドバイザー等)で構成し、今年度については、委員18名、顧問5名で構成しています。
特に、毎年11月に実施している会議では、次年度の新小学1年生、新中学1年生の児童生徒の特別支援の就学について協議することが主な内容となっています。実態把握や医師の診断、保護者の思い等を総合的に判断し、専門的な立場からの意見もいただき、就学の方向性を決定していく会議です。
また、現在、特別支援学級に在籍している児童生徒、通級による指導を受けている児童生徒についての現状と合理的配慮の状況等を委員、顧問に資料提案により確認していただき、協議を行っています。
5.「合理的配慮」とICT利用
二見議員 第5に、障害者差別解消法とそこに定められております「合理的配慮」についてお伺いします。
障害者差別解消法第8条2項は、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」 と定めています。
文科省は、この「合理的配慮」の具体例の一つとして「絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等の ICT 機器の活用」をあげています。
⑤当町の特別支援教育でICT機器はどのように利用されているか。また、本人および保護者がICT機器の利用を希望した場合の対応はどうしておりますでしょうか。
◆教育部長 現在、府中町内の特別支援学級及び通級指導教室において、状況に応じてICT機器を活用した授業を行っております。
例えば、自閉症・情緒障害特別支援学級において、国語の時間に、文字から具体的なイメージを持たせるよう、タブレットで写真を提示したり、理科の時間に、植物などをタブレットで提示したり、算数の図形において、実際に図形をタブレット上で見たりすることにより、イメージが持ちにくいものをしっかりとイメージさせ、理解を深めています。
次に「本人および保護者がICT機器の利用を希望した場合の対応について」ですが、
特別支援学級及び通級指導教室においては、現在もすでに個別の状況に応じて、ICT機器を利用した授業を実施しており、本人および保護者からICT機器の利用の希望があった場合は、実態に応じた利用は可能です。
しかし、通常の学級の一斉授業の場面において、発達障害の児童生徒が、タブレットを個別に使用することは容易でないと考えております。
今後、各学級に電子黒板が導入されることから、一斉授業の中で、電子黒板の活用により視覚的に思考を促したり、理解を深めたりする提示を行うことができます。このことは、クラス全員の理解を深めるとともに、発達障害の児童生徒への支援にもつながるものと考えております。


《第2回目》
二見議員 府中町における特別支援教育の現状について、大変よく分かりました。
特別支援学級に対して、町として独自の予算をつけ、教育支援員を配置しているという答弁でしたが、今年度は21クラス90人の児童生徒に対して30人の教育支援員を配置していると先日伺いました。障害の程度に応じ、ていねいに指導されていることをおおいに評価したいと思います。今後とも町費による特別支援員の加配を継続していただきたい。
①「合理的配慮」 2つの観点
私は今年の6月議会で「GIGAスクール構想と府中町の児童生徒の学習保障」について一般質問致しました。
これを読んだ保護者の方からメールをいただきました。文面からすると府中町ではないけれども広島県内にお住まいの方のようです。
その一部を紹介させていただきます。
「一人一人へのタブレット導入を、喉から手が出るほど望んでいる、一保護者です。タブレット導入が標準仕様でないから、書くことに困難、読むことが困難、音を拾うこと、何かしら型にはまった古い日本の学校教育のやり方に困難を抱え、学校に行けない子が、特別扱いは出来ないと、はねのけられる。広島は他県に比べ、とてもとても、遅れています。タブレットが遅くなるなら、他県の様に学習支援員を多く入れ、困難のある子に寄り添える人数を入れたらいい、それもできていない」
「親や子供の言うことを、学校は聞かないから、教育委員会がいいと言わないから、その子だけ使わせて、問題になるのが嫌だから、そうやってはねのける先生を専門家が一校一校説得していく、その大変さ、その気の遠くなる時間。ゆっくりじゃ遅いんです。早く、合理的配慮が遅れている広島に、タブレットを」。
「息子の様に板書も書けず、先生にメモをもらい、授業中は別の本を読んでいるように、と言われ、本を読むために学校に行っている子がいることを、知ってください」。
お子さんが学習障害で、授業でタブレットを使うことを強く望んでいることが分かります。
当町は「特別支援学級及び通級指導教室においては、現在もすでに個別の状況に応じて、ICT機器を利用した授業を実施しており、本人および保護者からICT機器の利用の希望があった場合は、実態に応じた利用は可能」とのことです。
メールをいただいた方のお子さんが、どういう学級に属されているのかは分からないのですが、府中町の場合は、特別支援学級と通級指導教室であれば、タブレットなどICT機器の利用はすでに行われているということですので、問題はクリアされているわけです。
しかし、学習障害をもっているお子さんが、特別支援学級でも通級指導教室でもない場合、「一斉授業の場面において、発達障害の児童生徒が、タブレットを個別に使用することは容易でない」という答弁でした。たしかにクリアすべき様々な課題があるように思われます。
先ほどの保護者の方が書かれているように、その理由が「特別扱いできない」ということであれば、それは乗り越えていく必要があるのではと思います。メガネや補聴器を特別扱いと思う同級生や保護者はいないと思います。ICT機器は学習障害をもっている児童生徒にとってメガネや補聴器と同じような役割を果たす場合がある。だから、その使用に対して「合理的配慮」が求められているのではないでしょうか。と同時に、ICT機器はメガネや補聴器と違う面もあります。多機能であることや、機器の使用によってそれぞれの障害を軽減する効果があるかどうかについて慎重な見極めがいるのではないかと思います。
小児科医の加藤醇子さんがタブレットの使用について「学習意欲が高まったことはとてもよかったのですが、タブレットやPCは補助具であり、特に音韻操作能力が低い場合、読み能力自体を著しく改善することはできません。改善の可能性がある低学年~中学年では、やはり専門的指導が必要です」*1と書いています。
*1)加藤醇子『ディスレクシア入門』日本評論社、194ページ
先日、学習障害についての講演会*2に参加しましたが、そこでも広島大学の氏間和仁准教授が「ICTの活用は、取り入れば良いわけではなく、指導のねらいを見極め、学びの本質に近づくための活用を目指したい」と述べていました。大切な観点だと思います。
*2)広島県発達障害専門家会議第5回シンポジウム「学習障害への気づきと支援~これまでの支援の成果と実績に学ぼう~」2020年11月1日
そこで質問ですが、
特別支援教育における「合理的配慮」について、町はどのように考えているのでしょうか。
◆学校教育課長 「合理的配慮」については、現在、特別な支援が必要な児童生徒について、保護者と連携を行いながら、個別の教育支援計画を作成し、教育支援員の配置や柔軟な教育課程の編成、教材を配慮するなどの支援を行っております。
先ほどありました一斉授業の場面において、発達障害の児童生徒がタブレットを個別に使用することについては、タブレット活用がその児童生徒にとって、支援として適しているかの見立てが必要であると考えており、また、一斉授業においては、授業者1名で学級の授業を行っていくことになるため、まわりの児童生徒やその保護者の理解、当該児童生徒のタブレットの活用力、また、一斉授業の流れの中で、適した活用ができるかなど、検討しなければならない事項が多くあります。
そのため、そうした要望があった場合には、専門家や関係機関の意見等も聞いた上で、個々の課題に合わせた支援が行えるよう多様な方法の検討をしていくことが必要かと考えています。
ICT機器を個別に使用しての授業については、先ほどお話したとおり、具体的にイメージを持たせるなどの活用を行っておりますが、その他にも、ICT機器を利用しプリント学習を行ったり、形をとらえる漢字練習に活用したりできるものと考えております。
②福祉部局との連携強化
二見議員 もう一つお尋ねしたいと思いますが、2017(平成29)年、文科省と厚労省は共同しての「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足させ、翌2018(平成30)年3月にプロジェクト報告をまとめました。
報告は「発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところであると述べ、「特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等(以下「障害児通所支援事業所等」という。)との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有が必要だと述べています。
そのために「各地方自治体の教育委員会や福祉部局――当町でいえば福祉保健部だと思いますが――が主導し、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進する」ことを課題としました。
この報告を踏まえ、2018(平成30)年、学校教育法施行規則に次のような規程が新設されました。
「特別支援学校に在学する幼児児童生徒について、個別の教育支援計画を作成することとし、当該計画の作成に当たっては、当該児童生徒等又は保護者の意向を踏まえつつ、関係機関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならないこととする」(新第134条の2関係)。
そして、この規程を特別支援学級、通級による指導を受けている児童生徒についても準用するとしています。
報告が言うように家庭を真ん中にして教育と福祉の連携を進めることは大切です。
そこで質問いたします。
報告には「国は、障害児通所支援事業所等と学校との関係を構築するため、各地方自治体において、教育委員会と福祉部局が共に主導し、「連絡会議」などの機会を定期的に設けるよう促す」とあるのですが、当町において、教育委員会と福祉保健部との定期的な協議の場というものはあるのでしょうか。また、日常的な連携はどうなっているでしょうか。
◆学校教育課長 現在、特別支援教育にかかって、障害児通所事業所等と学校との関係構築のための「連絡会議」を定期的に実施することは行っておりません。
しかし、障害児通所事業所と学校が、必要に応じて、連携会議やケース会議の実施や、個別に連携を図っております。
また、学校においては、特別支援学級の児童生徒、通級による指導を受けている児童生徒について、個別の教育支援計画、個別の教育指導計画を作成し、保護者の意向を踏まえつつ、当該児童生徒の支援に関する必要な情報を整理し、その上で、医療機関や福祉等と必要に応じて連携を図っています。
また、町では、県費によるスクール・ソーシャル・ワーカーを中学校区に1名ずつ配置し、月に1回教育委員会とスクール・ソーシャル・ワーカーとの連絡会議を実施しています。
スクール・ソーシャル・ワーカーは教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有し、家庭・学校・福祉をつなぐ重要な働きを担っており、児童生徒が抱える状況を改善・解決するための取り組みを行っております。
《第3回目》
二見議員 タブレットなどを使用したいという「要望があった場合には、専門家や関係機関の意見等も聞いた上で、個々の課題に合わせた支援が行えるよう多様な方法の検討」するということでした。決して門前払いでないということですので安心しました。
特別支援教育の充実のためにもっとも必要なことはなんでしょうか。香川県の小学校で特別支援学級の担任をされている先生が次のように書いています。
特別支援学級に対して「子どもたちは『ゆっくり勉強できる』『2回聞くとわかる』『先生が近くにいるから、困ったときに安心』と話してくれます。また、『音が少ないから集中できる』とも言います。この子たちは、少しの支援があれば、通常学級で学べるかもしれないと思うことがあります」。
「現在、進められようとしているインクルーシブ教育は、統合型――障害のある子どもが通常学級で学ぶこと――だと思います。統合型でおこなうのであれば、1学級の人数を15人くらいにし、複数担任にするか、構成メンバーに対して必要な支援員の配置が不可欠です。さらに、教室を広くし、クールダウンスペースや個別学習を展開するスペースを設けることも必要です。個々の児童の困り感に合わせて支援をしながら、個々の学びと集団での学びをコラボさせる、そんな環境が実現すれば、統合型も可能かもしれません。そして、学習指導要領の縛りはゆるくする必要があります」。*1
*1)濱田里実「子どもたちの発達に応じた学びの場の補償を」『クレスコ』2020年12月号
この先生が書かれているように、障害のある子どもが通常学級で学ぶことを保障するためにも、クラスの人数を減らし、複数担任とし、教育支援員を増やすことが必要だと思います。
文科省・町村会・府中町議会
文科省は少人数教育のためにずっと努力してきましたが、財務省の壁に阻まれてきました。10月26日、財務大臣の諮問機関である「財政制度審議会」作業部会においても全国一律での少人数学級の導入には否定的な意見が多数派を占めたようです*2。
*2)「毎日新聞」2020年10月27日付
これに対して萩生田文部科学大臣は27日の記者会見で「少人数学級を実施している自治体からの『意味がない』という声はただの一つもない」と反論したといいます。ぜひ、萩生田文科大臣をはじめ文科省には頑張っていただきたいと思います。
11月26日に開かれた全国町村長大会に向けてまとめられた要望書において次のような要望項目が掲げられました。
▼教員が子どもと向き合う環境を確保し、きめ細やかな指導を行うため、少人数学級や少人数指導、専科指導、生徒指導などの充実に向けて、複式学級の解消も含めた定数の改善を図ること。
▼通級指導や外国人児童生徒等への教育に係る基礎定数化については、安定的・計画的な配置が可能となるよう、着実に進めること。その際、へき地や対象児童生徒の少ない障害種などに対応する加配定数の削減は行わないこと。
▼小・中学校の普通学級に在籍する、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)など障害のある児童生徒に対する特別の指導(「通級による指導」)の充実や、日常生活上の介助や学習指導上のサポートを行う「特別支援教育支援員」配置の促進に向けた財政措置の拡充、関係機関との連携調整等を担う「特別支援教育コーディネーター」の専任化を推進するための教職員定数の改善、特別支援学級の編成基準の引下げなど、特別支援教育の充実を図ること。
いずれも大賛成です。
全国で200を超す議会が少人数学級を求める意見書を採択しています。
府中町議会も今定例会で「小中学校の全学年で少人数学級の実現を求める意見書」が採択される見通しです。
障害のあるなしにかかわらず、一人ひとりの状況に応じた教育を進めるために少人数学級ならびにそれを保障する教職員定数の改善が求められている。
この点で文科省も、全国町村会も、わが府中町議会も一致しているわけです。ぜひ文科省を励まし、それぞれの力を合わせて少人数学級を実現したい。
このことを最後に表明して私の質問を終わります。









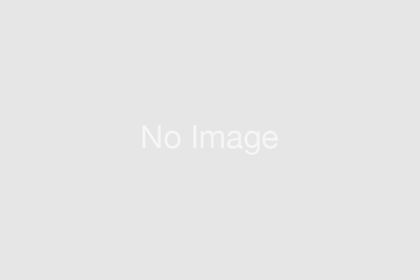


コメントを残す